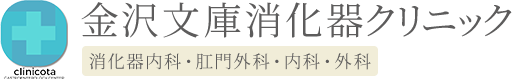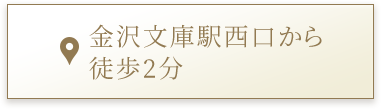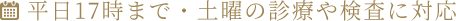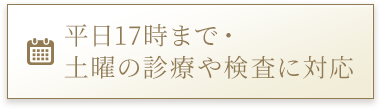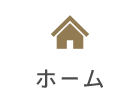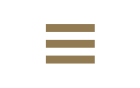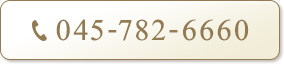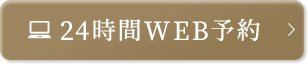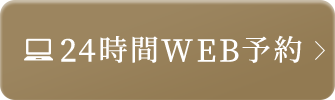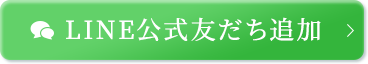消化器内科
 消化器内科では、食道・胃・腸・肝臓・胆のう・膵臓などの消化器疾患の診断と治療を行います。胃痛や胸やけ、腹痛、下痢・便秘、血便、食欲不振などの症状がある方はご相談ください。胃カメラや大腸カメラによる内視鏡検査を実施し、胃炎・ピロリ菌の除菌治療・胃潰瘍・日帰り大腸ポリープ切除・がんの早期発見に努めます。また、肝臓、胆のう、膵臓などの異常については、提携医療機関でCT・MRIなどの各種画像検査をおこない、精査することが可能です。消化器の不調を感じたら、お気軽にご相談ください。
消化器内科では、食道・胃・腸・肝臓・胆のう・膵臓などの消化器疾患の診断と治療を行います。胃痛や胸やけ、腹痛、下痢・便秘、血便、食欲不振などの症状がある方はご相談ください。胃カメラや大腸カメラによる内視鏡検査を実施し、胃炎・ピロリ菌の除菌治療・胃潰瘍・日帰り大腸ポリープ切除・がんの早期発見に努めます。また、肝臓、胆のう、膵臓などの異常については、提携医療機関でCT・MRIなどの各種画像検査をおこない、精査することが可能です。消化器の不調を感じたら、お気軽にご相談ください。
苦痛のない胃カメラ
 金沢文庫消化器クリニックでは胃内視鏡検査において鎮静剤、静脈麻酔を併用し検査をおこなうので、眠っている間に苦痛なく検査を受けることができます。咽頭反射、嘔吐反射はとてもつらいもので、2度と受けたくないという思いをされた方もいるかと思いますが、そのような方でもほとんど苦痛なく検査を受けることが可能です。
金沢文庫消化器クリニックでは胃内視鏡検査において鎮静剤、静脈麻酔を併用し検査をおこなうので、眠っている間に苦痛なく検査を受けることができます。咽頭反射、嘔吐反射はとてもつらいもので、2度と受けたくないという思いをされた方もいるかと思いますが、そのような方でもほとんど苦痛なく検査を受けることが可能です。
日帰り大腸ポリープ切除
 がん化しうるポリープは発見次第切除することが望ましく、 小さい段階で腺腫性ポリープを切除することで大腸がんによる死亡率を低下させることができます。また、ポリープが除去、確認された後、再発を防ぐための定期的な大腸内視鏡検査(大腸カメラ)が推奨されます。再発のリスクは、以前に摘出されたポリープの数、サイズ、型、細胞の変性程度などによって異なります。
がん化しうるポリープは発見次第切除することが望ましく、 小さい段階で腺腫性ポリープを切除することで大腸がんによる死亡率を低下させることができます。また、ポリープが除去、確認された後、再発を防ぐための定期的な大腸内視鏡検査(大腸カメラ)が推奨されます。再発のリスクは、以前に摘出されたポリープの数、サイズ、型、細胞の変性程度などによって異なります。
消化器の主な病気
逆流性食道炎
 胃食道逆流症(Gastroesophageal Reflux Disease、GERD)は、胃酸や胃内容物が食道に逆流することによって引き起こされる慢性的な炎症性疾患です。通常、胃酸は胃の中にとどまり、食道という食物が口から胃に流れる管は、その内壁が胃酸から保護されています。しかし、GERDの場合、この胃酸や消化液が食道に逆流し、食道の内壁にダメージを与え、炎症を引き起こします。食道に炎症があるものを逆流性食道炎(reflux esophagitis)と呼びます。GERDは自覚症状と内視鏡検査によって診断されます。
胃食道逆流症(Gastroesophageal Reflux Disease、GERD)は、胃酸や胃内容物が食道に逆流することによって引き起こされる慢性的な炎症性疾患です。通常、胃酸は胃の中にとどまり、食道という食物が口から胃に流れる管は、その内壁が胃酸から保護されています。しかし、GERDの場合、この胃酸や消化液が食道に逆流し、食道の内壁にダメージを与え、炎症を引き起こします。食道に炎症があるものを逆流性食道炎(reflux esophagitis)と呼びます。GERDは自覚症状と内視鏡検査によって診断されます。
GERDは長期間続く場合、合併症を引き起こす可能性があります。例えば、食道狭窄(食道の狭まり)、バレット食道(食道内壁の異常な変化)、食道がんのリスクが増加することがあります。治療は、薬物療法、ライフスタイルの変更(食事療法、体重管理、禁煙など)、または手術が必要な場合があります。GERDの症状を持つ場合、医師に相談し、適切な治療オプションを検討することが重要です。
ヘリコバクター・
ピロリ感染症
ヘリコバクター・ピロリ感染症は、胃の粘膜に生息するヘリコバクター・ピロリ(Helicobacter pylori)という細菌が原因で起こる感染症です。この細菌は胃酸の影響を受けずに胃の粘膜に生息し、胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍を引き起こすことがあります。さらに、長期にわたる感染は胃がんのリスクを高める可能性があります。
ヘリコバクター・ピロリは主に口から口への接触や、汚染された食物や水の摂取によって人から人へと伝播します。多くの感染者には特有の症状が現れないため、自覚症状がなくても感染していることがあります。しかし、感染が胃潰瘍や十二指腸潰瘍を引き起こした場合、腹痛、胃の不快感、胸やけ、吐き気などの症状が現れることがあります。
診断は、便中のヘリコバクター・ピロリ抗原の検査、血液検査、胃内視鏡検査による組織採取とその細菌の培養、呼気試験などによって行われます。治療は、通常、抗生物質と胃酸の分泌を抑える薬剤を組み合わせた二重または三重療法で行われ、感染の除去と関連症状の改善を目指します。
急性胃炎
 急性胃炎とは、胃の粘膜に急性の炎症が起こる病気です。胃の粘膜は、胃酸から胃を守っている大切なバリアの役割を果たしていますが、このバリアが何らかの原因で損傷を受けると、炎症が起こり、様々な症状が現れます。
急性胃炎とは、胃の粘膜に急性の炎症が起こる病気です。胃の粘膜は、胃酸から胃を守っている大切なバリアの役割を果たしていますが、このバリアが何らかの原因で損傷を受けると、炎症が起こり、様々な症状が現れます。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃潰瘍と十二指腸潰瘍は、どちらも胃酸によって胃や十二指腸の粘膜が傷つき、潰瘍(かいよう)と呼ばれる深い傷ができる病気です。これらをまとめて消化性潰瘍(peptic ulcer)と呼ぶこともあります。
萎縮性胃炎
萎縮性胃炎とは、胃の粘膜が慢性的な炎症によって薄くなり、萎縮してしまう病気です。胃の粘膜は、胃酸を分泌したり、食べ物を消化するのに重要な役割を果たしています。この粘膜が萎縮することで、これらの機能が低下し、様々な症状が現れることがあります。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアは、特定の器質的な異常が見つからない胃の機能障害を指す用語です。ディスペプシアは、一般的には上腹部不快感や痛み、満腹感、早期飽満感、膨満感、嘔気などの症状を特徴とします。機能性ディスペプシアは、患者の症状と関連した特定の器質的異常が存在しない場合に診断されます。つまり、内視鏡や検査によって胃の病的な異常が見つからない場合でも、患者の症状が持続する場合に適用される診断です。
この状態の原因ははっきりとはわかっていませんが、胃の運動や胃酸分泌の異常、胃粘膜の感受性の変化、神経・筋肉の機能異常、ストレスなどが関与している可能性があります。また、食事の刺激や心理的要因も症状を悪化させる要因として関連していることがあります。
便秘症
 便秘とは、本来体外へ排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態です。便秘の目安としてよく言われるのは、「排便が1週間に3回未満」もしくは「3日以上排便がない、または毎日排便があっても残便感がある場合」です。慢性便秘とは、長期間にわたって便秘の症状が続く状態を指します。慢性便秘の場合、これらの症状が数週間以上続くことが一般的です。便秘は個人によって異なる期間で起こる場合がありますが、一般的に頻度の低下、便の硬化、腹痛や膨満感、強い排便努力、不完全排便などの特徴があります。便秘の原因はさまざまで、食事、運動不足、ストレス、薬の副作用、慢性的な病気などが関連していることがあります。便秘は一時的なものから慢性的なものまで幅広い症状を持つため、原因を特定して適切な治療を行うことが重要です。
便秘とは、本来体外へ排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態です。便秘の目安としてよく言われるのは、「排便が1週間に3回未満」もしくは「3日以上排便がない、または毎日排便があっても残便感がある場合」です。慢性便秘とは、長期間にわたって便秘の症状が続く状態を指します。慢性便秘の場合、これらの症状が数週間以上続くことが一般的です。便秘は個人によって異なる期間で起こる場合がありますが、一般的に頻度の低下、便の硬化、腹痛や膨満感、強い排便努力、不完全排便などの特徴があります。便秘の原因はさまざまで、食事、運動不足、ストレス、薬の副作用、慢性的な病気などが関連していることがあります。便秘は一時的なものから慢性的なものまで幅広い症状を持つため、原因を特定して適切な治療を行うことが重要です。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群(IBS)の診断には、ローマ基準(Rome Criteria)と呼ばれる診断基準が使用されます。これは国際的に受け入れられている診断基準であり、主なIBSの症状を定義しています。
ローマ基準によると、IBSの診断には以下の条件が必要です:
最近3ヶ月間、月に4日以上腹痛や腹部不快感が繰り返し起こり、次の項目の2つ以上があること。
- 排便と症状が関連する(排便後に症状が軽快するなど)
- 排便頻度の変化を伴う
- 便性状の変化(便秘や下痢)を伴う
- 期間としては6ヶ月以上前から症状がある
これらの基準が満たされている場合、IBSの診断が行われる可能性があります。ただし、他の潜在的な病気を除外するために、病歴を詳しく聞き取り、身体検査や必要に応じて検査を行うことが重要です。IBSは他の病気や身体的な問題による症状と類似している場合があるため、正確な診断を得るためには専門医の指導が必要です。
クローン病
クローン病(Crohn's disease)は、消化管に慢性的な炎症を引き起こす疾患です。この炎症は、口から肛門に至る消化管のどの部分にも発生する可能性がありますが、最も一般的には小腸の最後の部分と大腸の最初の部分で見られます。
クローン病の主な症状には以下のものがあります:
- 腹痛や痙攣
- 慢性的な下痢、場合によっては血便
- 体重減少
- 疲労感
- 栄養不良
クローン病の原因は完全には明らかになっていませんが、免疫系の異常、遺伝的要因、環境因子が関連していると考えられています。現在、この病気に対する根治治療は存在せず、治療は症状の管理と合併症の予防に重点を置いています。
治療法には、抗炎症薬、免疫調節薬、生物学的製剤などの薬物療法、場合によっては外科手術が含まれます。また、食生活の調整も重要で、特定の食品が症状を悪化させる場合があるため、個々の患者に合わせた食事療法が推奨されることがあります。
クローン病は慢性疾患であり、寛解と再発を繰り返すことが一般的です。したがって、定期的な医療フォローアップと適切な治療計画の維持が重要です。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は大腸粘膜の炎症により、びらんや潰瘍が発生する病気です。原因は不明であり、現在のところ根治療法は存在しません。この病気は厚生労働省によって難病に指定されていますが、専門医の管理のもと適切な治療を行っていけば、通常の生活を送ることが可能です。 潰瘍性大腸炎は大腸に限定された炎症を引き起こしますが、クローン病は消化管のいたる部分に炎症が起こります。
食道がん
食道がんは、食道の組織に発生する悪性腫瘍です。食道は、喉から胃にかけて食べ物を運ぶ管です。この種のがんは、食道の内側の細胞が異常に成長し、コントロールできなくなった状態を指します。食道がんは、その発生する場所によって、扁平上皮がんと腺がんの二つの主要なタイプに分けられます。
扁平上皮がん
食道の上部および中部で一般的に見られ、食道の内側を覆っている扁平上皮細胞から発生します。
腺がん
食道の下部、特に胃との接合部近くでよく見られます。これは、食道の腺細胞が変化して発生します。
食道がんのリスク要因には、喫煙、過度のアルコール消費、慢性的な食道炎、バレット食道(胃酸の逆流によって食道の細胞が変化する状態)、肥満、不健康な食生活などがあります。初期段階では症状がほとんどないことが多いですが、進行すると食べ物を飲み込む際の痛みや困難、体重減少、胸痛、咳、声のかすれなどの症状が現れることがあります。
食道がんの診断は、内視鏡検査、バリウムX線検査、生検などによって行われます。治療法はがんのタイプ、進行度、患者の健康状態などによって異なり、手術、放射線療法、化学療法、あるいはこれらの組み合わせが考慮されます。早期発見と治療が重要で、がんの拡散を防ぎ、治療の効果を高めることができます。
胃がん
胃がんは、胃の壁の一番内側の粘膜から発生するがんです。胃がんのほとんどは「腺がん」と呼ばれるがんであり、腺がんは、細胞と組織の構造的特徴から、分化型と未分化型に大別されます。胃がんは、大きくなるにつれて、徐々に胃の壁の外側に深く浸潤していきます。がんがより深く浸潤するにつれ、リンパ節や他臓器に転移するリスクが高まり、胃の外側にある大腸や膵臓、腹膜にも直接広がっていくことがあります(転移・直接浸潤・播種)。
大腸がん
大腸がんは、大腸(結腸と直腸)の粘膜細胞が異常に増殖してできるがんのことを指します。大腸がんは、世界中でのがんによる死因の中でも上位に位置しており、早期発見と治療が非常に重要です。大腸がんは早期に発見すると、治癒の可能性が高くなるため、リスク因子に該当する人や好発年齢(40歳以上)に達した人は、定期的なスクリーニングを受けることが推奨されます。
大腸ポリープ
大腸ポリープは、大腸(結腸や直腸)の内壁から突出した成長物や腫瘍の一種です。大腸ポリープは良性のものが多いですが、一部のポリープはがんへと進展するリスクを持っています。 腺腫は、大腸上皮(腺管)が腫瘍性に増殖したもののうち良性のものを言い、大腸ポリープの約8割を占めます。大腸がんは、もともと大腸がんとして発生するもの(de novo)の他に、この腺腫を含む前がん病変(がんの前段階の病変)と言われる良性病変から進展するものがあり、数的には後者が多いとされています。
大腸ポリープの発見と早期治療は、大腸がんの予防に非常に重要です。小さなポリープは無症状で、発見されているポリープのほとんどが大腸内視鏡(大腸カメラ)検査で偶然に発見されています。 大腸がんになる可能性のあるポリープをより早期に発見するためには、症状がないうちでも大腸内視鏡(大腸カメラ)検査を中心としたがん検診を受けることが重要です。また、リスク因子に当てはまる場合や、推奨される年齢(40歳以上)に達した場合は、定期的な大腸がん検診や大腸内視鏡検査を受けることを考慮すべきです。