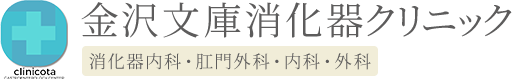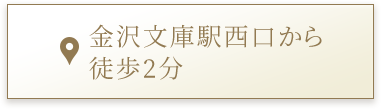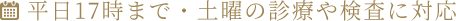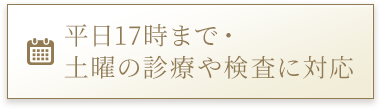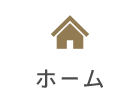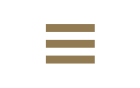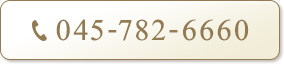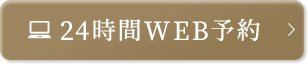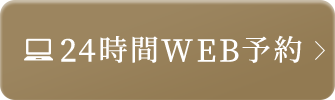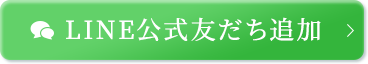コロナワクチン接種は
実施しておりません
帯状疱疹ワクチン
帯状ワクチンとは?
 帯状疱疹ワクチンは、帯状疱疹(ヘルペス・ゾスター)を予防し、発症時の症状の軽減や合併症のリスクを下げるためのワクチンです。帯状疱疹は、水ぼうそうの原因である**水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)**が体内に潜伏し、免疫力の低下により再活性化することで発症します。
帯状疱疹ワクチンは、帯状疱疹(ヘルペス・ゾスター)を予防し、発症時の症状の軽減や合併症のリスクを下げるためのワクチンです。帯状疱疹は、水ぼうそうの原因である**水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)**が体内に潜伏し、免疫力の低下により再活性化することで発症します。
帯状疱疹とは?
- 主に50歳以上の成人に多く発症し、強い痛みや発疹を伴う。
- **神経痛(帯状疱疹後神経痛: PHN)**が後遺症として残ることがあり、数ヶ月~数年続くこともある。
- 免疫力が低下したとき(加齢、ストレス、病気)に発症しやすい。
帯状疱疹ワクチンの種類
現在、帯状疱疹ワクチンには2種類あります。
1. シングリックス(Shingrix)【組換えワクチン】
適応
50歳以上の成人。
接種回数
2回接種(2か月間隔)。
効果
帯状疱疹発症を約 90%以上予防、PHNのリスクも大幅に軽減。
持続期間
10年以上の予防効果が期待できる。
特徴
生ワクチンではないため、免疫が低下した人でも接種可能。
副作用
接種部位の痛み、腫れ、倦怠感、軽度の発熱(1~3日で改善)。
2. 乾燥弱毒生水痘ワクチン
(ビケン)【生ワクチン】
適応
50歳以上の成人。
接種回数
1回接種。
効果
帯状疱疹発症を50~60%予防、PHNのリスクを軽減。
持続期間
約5年程度(シングリックスより短い)。
特徴
免疫力が低下した人には推奨されない(生ワクチンのため)。
副作用
注射部位の腫れや痛み、軽度の発熱。
接種対象者と推奨
- 50歳以上の人は帯状疱疹のリスクが上がるため接種推奨。
- 免疫低下者(糖尿病、がん治療中の人など)はシングリックスが適している。
- 帯状疱疹にかかったことがある人も再発予防のために接種可能。
- どちらのワクチンも水ぼうそうの既往がある人が対象(未感染者は不要)。
まとめ
- 帯状疱疹は50歳以上の成人で発症リスクが高まり、強い痛みや神経痛を引き起こす。
- シングリックス(2回接種)は高い予防効果(90%以上)と長期持続(10年以上)が期待できる。
- 生ワクチン(1回接種)は手軽だが、免疫低下者には不向きで効果もやや低い。
- 免疫力が低下している人、帯状疱疹経験者にもワクチン接種が推奨される。
50歳を超えたら、帯状疱疹の予防としてワクチン接種を検討することが推奨されます。
当院では50歳以上の成人を対象に、遺伝子組換え型ワクチンであるシングリックス接種をおこなっています。
乾燥弱毒水痘ワクチン接種はおこなっていません。
| 対象 | 50歳以上の成人 |
|---|---|
| 接種回数 | 2回(1回目の接種から2か月後に2回目の接種を行う) |
| 費用 | 22000円/回(自費、税込み) |
| 予約 |
予約制(電話)です。 |
B型肝炎ワクチン
B型肝炎ワクチン(HBVワクチン)は、B型肝炎ウイルス(HBV)による感染を予防するためのワクチンです。B型肝炎は、肝炎、肝硬変、肝がんの原因となる可能性があり、特に慢性化すると重篤な肝疾患を引き起こすことがあります。
B型肝炎の感染経路
- 血液・体液を介した感染(輸血、注射器の共有、刺青・ピアスなど)。
- 母子感染(出産時に母親から新生児へ感染)。
- 性的接触(体液を通じた感染)。
B型肝炎ワクチンの特徴
目的
B型肝炎ウイルスへの免疫を獲得し、感染予防および重症化の防止。
成分
遺伝子組換え型ワクチン(ウイルスの一部を人工的に作り、免疫を誘導)。
接種対象
乳児、医療従事者、感染リスクの高い人(注射薬使用者、透析患者など)。
接種スケジュール
1.乳児の定期接種(日本)
対象
- 2016年4月1日以降に生まれたすべての乳児。
スケジュール
生後2か月、3か月、7~8か月の計3回接種。
2.成人の任意接種
対象
未接種の人、感染リスクが高い人(医療従事者、家族にキャリアがいる場合など)。
スケジュール
0ヶ月、1ヶ月後、6ヶ月後の3回接種。
効果と持続期間
- 3回接種することで、約95%以上の人が免疫を獲得。
- 免疫の持続期間は通常10年以上(長期的な効果あり)。
- 乳幼児期に接種すると、一生涯の感染リスクを低減。
副作用と注意点
一般的な副作用
- 接種部位の腫れ、痛み、発赤
- 発熱、倦怠感、頭痛
まれな副作用
- アレルギー反応(アナフィラキシー)
- 筋肉痛や関節痛
まとめ
- B型肝炎ウイルスの感染予防と重症化を防ぐ重要なワクチン。
- 2016年以降、日本では乳児の定期接種として導入。
- 成人でも3回接種で高い予防効果が得られる。
- 医療従事者や感染リスクのある人には特に推奨。
B型肝炎は慢性化すると肝がんのリスクがあるため、ワクチン接種は有効な予防手段となります。
成人でのB型肝炎ワクチン接種の推奨される人
-
医療関係者
-
医療以外で血液や血液製剤にさらされる可能性のある方
-
B型肝炎の方と性的パートナーの方や同居家族
-
複数の性的パートナーをもつ方
-
頻繁に輸血や血液製剤を投与する必要がある方、透析患者・臓器移植を受けた方
B型肝炎ワクチンの接種を
受けることができない人
以下の方はB型肝炎ワクチンを接種することができません。
-
明らかな発熱(通常37.5℃以上)がある方
-
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
-
本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな方
-
上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある方
当院では成人を対象にヘプタバックス-Ⅱ®の接種をおこなっています。
| 対象 | 50歳以上の成人 |
|---|---|
| 接種回数 | 3回(1回目の接種から1か月後に2回目の接種、6ヶ月後に3回目の接種をおこなう) |
| 費用 | 6600円/回(自費、税込み) |
| 予約 |
予約制(電話)です。 |
RSワクチン
RSウィルスとは?
 RSウイルスは、正式には呼吸器合胞性ウイルス(Respiratory Syncytial Virus、RSV)と呼ばれ、特に乳幼児や高齢者に重症の呼吸器感染症を引き起こすことで知られています。RSウイルスは世界中で見られ、秋から春にかけての冷え込む季節に流行することが多いです。
RSウイルスは、正式には呼吸器合胞性ウイルス(Respiratory Syncytial Virus、RSV)と呼ばれ、特に乳幼児や高齢者に重症の呼吸器感染症を引き起こすことで知られています。RSウイルスは世界中で見られ、秋から春にかけての冷え込む季節に流行することが多いです。
このウイルスによる感染症は、軽い風邪の症状から始まることが多く、鼻水、咳、発熱などが見られますが、乳幼児や高齢者、免疫系が弱っている人では、重度の肺炎や気管支炎に進行するリスクがあります。特に、乳幼児では重症の呼吸困難を引き起こすことがあり、注意が必要です。
RSウイルス感染症の治療には特定の薬が承認されているわけではありませんが、症状の緩和や合併症の予防のために、支持療法(十分な休息、水分補給など)が推奨されます。また、重症の場合は入院治療が必要になることもあります。
RSウィルスワクチンとは?
2023年9月に、60歳以上の方を対象としたRSウイルスワクチン「アレックスビー」が日本国内で初めて承認されました。このワクチンは、高齢者がRSウイルスに感染して気管支炎や肺炎を発症するリスクを約80%減らす効果があります。特に、基礎疾患(慢性閉塞性肺疾患・気管支喘息といった呼吸器の病気、糖尿病、慢性心不全、進行した肝臓や腎臓の病気)のある高齢者への有効性が期待されています。アレックスビーの1回接種で2-3年の有効期間があります。接種は任意ですが、特に心不全や慢性閉塞性肺疾患、糖尿病などをお持ちの60歳以上の方は、積極的に接種をご検討ください。費用は26,000円(自費)です。
インフルエンザワクチン
 インフルエンザワクチンとは、インフルエンザウイルスによる感染を予防し、重症化を防ぐためのワクチンです。ウイルスの変異に対応するため、毎年流行する型に合わせて製造され、定期的な接種が推奨されています。
インフルエンザワクチンとは、インフルエンザウイルスによる感染を予防し、重症化を防ぐためのワクチンです。ウイルスの変異に対応するため、毎年流行する型に合わせて製造され、定期的な接種が推奨されています。
インフルエンザワクチンの
特徴
1.目的
インフルエンザの感染予防および重症化防止。
2.成分
不活化ワクチン(死滅したウイルスを使用)または弱毒化ワクチン(生きたが弱められたウイルスを使用)。
3.効果
- 感染のリスクを減らす。
- 発症した場合も症状を軽減。
- 集団免疫の形成に寄与。
4.接種対象
- 高齢者、幼児、妊婦、基礎疾患のある人など、重症化リスクの高い人に特に推奨。
- 医療従事者や集団生活を送る人も推奨対象。
接種方法
- 通常 年1回の接種(流行前の秋~冬に接種)。
- 子ども(13歳未満)は2回接種が推奨される場合あり。
副作用と注意点
一般的な副反応
接種部位の腫れ、発熱、倦怠感など(通常1~2日で回復)。
まれな副作用
アレルギー反応(アナフィラキシーなど)。
注意点
卵アレルギーのある人は医師と相談。
まとめ
インフルエンザワクチンは、個人だけでなく社会全体の健康を守るために重要な予防策です。特に流行が始まる前(秋頃)の接種が推奨されています。
インフルエンザワクチンの開始時期、費用は季節毎にお知らせします。
肺炎球菌ワクチン
肺炎球菌ワクチンとは?
肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)による感染症を予防するためのワクチンです。肺炎球菌は肺炎をはじめ、中耳炎、髄膜炎、敗血症などの重篤な感染症を引き起こす細菌であり、特に高齢者や免疫力の低い人にとって重大なリスクとなります。
肺炎球菌ワクチンの種類
肺炎球菌ワクチンには大きく分けて2種類あります。
1.PPSV23
(ニューモバックスNP)
23価肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン(Pneumococcal Polysaccharide Vaccine, 23-valent)
特徴
- 23種類の肺炎球菌型に対応し、主に高齢者向け。
効果
- 肺炎球菌感染症の予防および重症化の抑制。
対象
65歳以上の人に定期接種として推奨。
接種頻度
5年ごとに1回接種が可能。
2.PCV13(プレベナー13)
13価肺炎球菌結合型ワクチン(Pneumococcal Conjugate Vaccine, 13-valent)
特徴
- 13種類の肺炎球菌型に対応し、免疫が弱い人や乳幼児向け。
効果
より強い免疫記憶を形成し、長期間の予防効果が期待される。
対象
2歳未満の乳幼児や基礎疾患のある成人。
接種頻度
乳幼児は生後2か月から計4回接種。成人は医師の判断で追加接種。
効果と対象者
効果
- 肺炎球菌感染症の発症を抑制。
- 特に重症化を防ぐ効果が期待される。
- PCV13はより強い免疫反応を引き起こすため、免疫力の弱い人には効果的。
推奨対象者
- 65歳以上の高齢者(PPSV23が定期接種)。
- 慢性疾患(糖尿病、心疾患、慢性肺疾患など)を持つ人。
- 脾臓摘出後の人、免疫不全の人。
- 乳幼児(PCV13が定期接種)。
副作用と注意点
一般的な副作用
- 接種部位の腫れ、痛み、赤み(数日で改善)。
- 軽度の発熱や倦怠感。
まれな副作用
- アレルギー反応(アナフィラキシー)。
- 発熱や強い倦怠感が長引く場合は医師に相談。
まとめ
- 肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌感染症を防ぐために重要なワクチン。
- PPSV23(23価)は高齢者向け、PCV13(13価)は乳幼児・免疫低下者向け。
- 65歳以上の高齢者には定期接種が推奨されている。
- 接種によって感染リスクの低減、重症化の防止が期待できる。
肺炎は高齢者の主要な死因の一つであり、ワクチン接種は重要な予防策となります。
当クリニックではニューモバックスの接種のみおこなっています。
費用
| 自費 | 7,800円 |
|---|---|
| 公費 | 3,000円 |